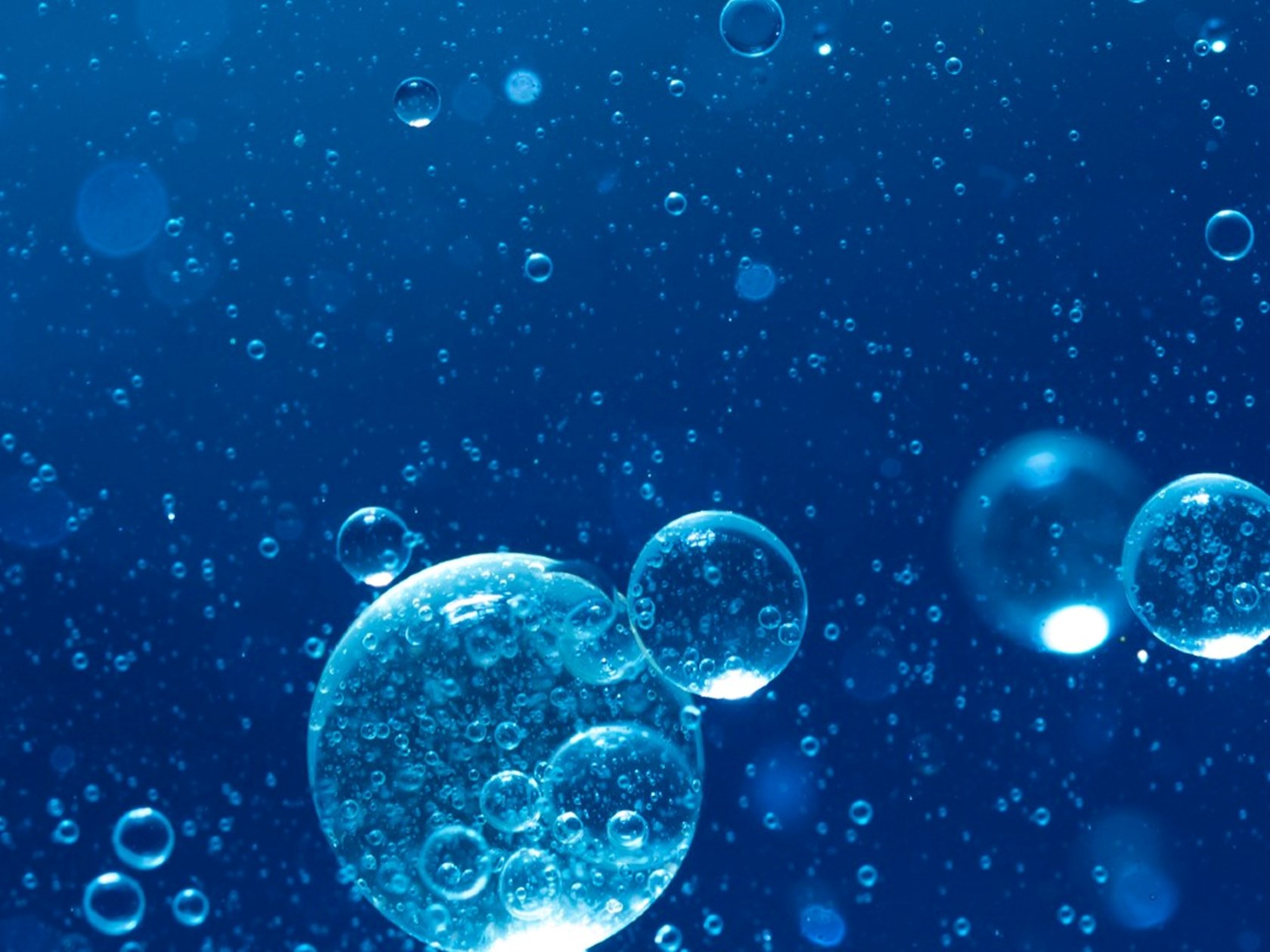平成29(2017)年に改正された土壌汚染対策法(土対法)の施行(平成30(2018)年、または平成31(2019)年)から5年経過後の令和6(2024)年度から次の法改正を見据えた土対法の施行状況の確認・見直しが環境省にて行われています。令和7(2025)年の夏~秋ごろに環境大臣への答申の取りまとめが予定されており、作業が順調に進めば令和8(2026)年に土対法が改正される可能性があります。法の見直しの議論を行っている中央環境審議会 水環境・土壌農薬部会 土壌制度小員会では、2025年5月までに次の7つの論点が挙げられ審議されています。
- 汚染情報に係る調査契機について
- 健康リスクに応じた試料採取等調査について
- 汚染土壌の管理票について
- ただし書の確認を受けた土地の形質の変更の際の調査報告について
- 調査費用の汚染原因者への求償について
- 健康リスクに応じた自然由来等基準不適合土壌の取扱について
- その他(有害物質使用特定事業場における事故発生時の対応について など)
これらの論点の中から土対法に規定される特定有害物質を取り扱う事業者や土地所有者への影響が比較的大きいと予測される以下の4点について説明いたします。なお、以下に挙げる論点は審議中であり、その内容が実際に改正法に反映されるかどうかは確定したものではありません。
汚染情報に係る調査契機について
主に有害物質使用特定施設の使用廃止時(法第3条)、一定規模以上の土地の形質の変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認める時(法第4条)、あるいは土対法に準じた自主調査を行う際に、対象地の地歴情報の収集が行われていますが、事業者や土地所有者に情報の保存の責務がなく、企業の統廃合、土地所有者の変更・高齢化などによる情報の散逸が地歴調査を困難にしています。そこで見直しの方向性として、①法第3条第1項のただし書の確認を受ける(有害物質使用特定施設を廃止するが操業を継続することで土壌汚染状況調査を一時的に免除してもらう)、②有害物質使用特定施設の承継、③有害物質使用特定事業場の土地所有者の変更(土地の切り売りを含む)の契機に、土地の所有者等に必要な情報の把握を行うことを義務づけ、都道府県等に届出することが議論されています。
この論点が改正法に盛り込まれた場合は、地歴情報の保存・管理や新設される契機(前掲の①から③)での届出対応が事業者等に求められることになるため、M&A等によるアセットや事業の譲渡時にも地歴調査の実施などが必要となる可能性があります。
健康リスクに応じた試料採取等調査について
有害物質使用特定施設の使用廃止時、および一定規模以上の土地の形質の変更などの土対法の調査契機に該当した際には、現行法では健康リスクがない場合でも試料採取等調査(土壌等の採取と分析)の実施が必要であり、土壌汚染が判明すると健康リスクの有無に関係なく汚染がある区域(要措置区域等)として指定されます。そこで、引き続き工場・事業場の敷地として利用される場合に、地下水モニタリングを実施して一定期間、健康リスクがないことが確認できれば試料採取等調査を一律に義務づけないことが議論されています。なお、試料採取等調査を行わない場合に汚染土壌が適正に処理されることを担保するために、敷地外に土壌を搬出する場合は搬出前に土壌汚染の有無を確認することや、形質変更の実施中および終了後の一定期間において地下水モニタリングを実施することも議論されています。
土対法は人の健康被害防止を目的とした法律ですので、より法の趣旨に近づく議論の方向性だと考えられます。特定有害物質を取り扱う事業者にとっては、地下水モニタリングを日常の環境管理として実施するだけではなく、将来の土地の形質変更や特定施設の廃止時に調査費用の負担を軽減させる効果も考えられます。また、地下水モニタリングに積極的に取り組む事業者が増えることも考えられ、汚染の早期発見と拡散防止に寄与することも期待されます。
調査費用の汚染原因者への求償について
現行の土対法では、要措置区域において汚染の除去等の措置に要した費用については、土地の所有者等は汚染原因者に請求することが可能(法第8条第1項)となっていますが、土壌汚染状況調査に要した費用については規定がなく、汚染原因者に請求するには民法上の責任を明らかにし損害賠償を求める必要があります。見直しの議論においては、法に基づく土壌汚染状況調査を行った場合に、要措置区域だけではなく形質変更時要届出区域であっても汚染原因者に調査費用を請求することができる(一定の期間で時効)としてはどうかとされています。背景としては、調査コストの負担が大きく、場合によっては措置と同規模の費用となるケースも少なくないことが挙げられています。
過去の土地所有者や占有者が客観的に汚染原因者とみなされる場合に、現在の土地の所有者等が土壌汚染状況調査に要した費用を汚染原因者に請求するハードルが下がるものと予測されます。
有害物質使用特定事業場における事故発生時の対応について
有害物質使用特定事業場で漏洩等の事故が発生した場合、水質汚濁防止法では応急措置と事故内容の届出が義務付けられていますが、土対法における対応は求められていません。そこで、土対法における事故時の対応の必要性について見直しが検討され、方向性としては、事故発生を土対法の新たな調査契機とはしない一方で、①自治体内において当該事故に関する情報を、公共用水域や地下水に係る常時監視担当者や、土壌汚染対策法担当部署等に共有すること、②必要に応じて土壌汚染状況調査の報告を受けた際等に、土壌汚染対策法担当部署等にてその結果を活用すること、が議論されています。
この論点が改正法に反映された場合、水質汚濁防止法の対応が必要な事故が発生した場合、その履歴や内容は自治体の土対法担当部署にも共有されることから、事故の内容や対応結果は、将来の地歴調査や土壌汚染状況調査に反映することが必要と考えられ、事故履歴等を適切に保存・管理していくことがより求められることになるのではないかと考えられます。
ERMでは、土壌・地下水汚染をはじめとする様々な環境債務に関して、国内外を問わず、以下に示すような詳細な調査や対策を提供すると共に、問題の解決に向けたコンサルティングサービスを通じてクライアント様のビジネスを支援しています。
- 土壌地下水の調査、浄化や修復工事
- 土壌汚染対策法や環境に係る条例に関連する行政手続き・交渉の支援サービス
- 工場閉鎖時の建屋解体工事や有害物質(アスベスト・化学物質)の除染・除去工事
- PFAS等の新規規制物質に対する国内外の最新技術を使用した調査や浄化工事
ダウンロードはこちら